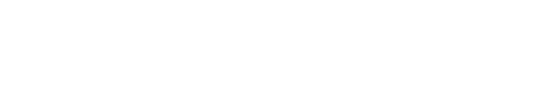出生前検査認証制度等
運営委員会設置の経緯について
出生前検査認証制度等運営委員会とは
「出生前検査認証制度等運営委員会」(以下、当委員会)は、出生前検査を受ける妊婦さんとパートナーへのサポート体制、遺伝カウンセリングや検査の質や正確さをより確かなものにするために設けられた組織です。
当委員会には、産婦人科医、小児科医、臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー、看護師、助産師、保健師、先天的な病気のある子どもを育てている親、社会学者、ジャーナリストなど、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーがいます。

設立は2021年で、国の専門委員会(厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会NIPT等の出生前検査に関する専門委員会※)の提言に基づき、日本医学会に設けられました。
出生前検査についての情報提供、NIPTを実施する施設認証、検査精度評価などの機能を担っており、国の専門委員会と連携をとりながら運営されています。
(※2023年4月、こども家庭庁発足により同庁に移管)
なぜ出生前検査にはサポートや認証制度が必要なのでしょう。
出生前検査は、検査そのものや、検査によって得られる結果を正しく理解し、その後の計画を考えていくなかで、さまざまな心配や迷いが生じやすい検査です。そのため、出生前検査は、妊婦さんとパートナーのために、出生前検査の専門家による充実したサポート体制のもと実施することが大切です。
専門家のサポート体制が整っているかどうかを、妊婦さんとそのパートナーがすぐにわかるように、出生前検査認証制度等運営委員会は、NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)を提供しようとする施設から提出された申請内容を審査し、条件を満たした施設を認証しています。
NIPTの導入から当委員会設立までの経緯
NIPTは、日本産科婦人科学会が策定した「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指針」に基づき、2013年、認定された少数の施設での臨床研究として開始されました。しかし、この枠外で、学会の指針に基づかない医療機関でのNIPTの実施が増加し、それに伴って適切な遺伝カウンセリングが行われないケースも増えてきました。

この問題に対処するために、厚生労働省は2019年から2020年にかけて「母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)の調査等に関するワーキンググループ」を設立し、NIPTの状況を検討しました。そして2020年には厚生労働省厚生科学審議会の下にNIPT等の出生前検査に関する専門委員会が設置され、翌年、新たな認証制度と、妊婦さん、パートナーへの情報提供の必要性等を提唱する報告書が作成されました。これらの任務を担ったのが、当委員会です。
当委員会のウェブサイトを訪れることで、妊婦さんとパートナーは出生前検査についての理解を深め、信頼性の高い認証施設や、サポートを受けられるところを見つけることができます。
出生前検査についての基本的な考え方
出生前検査の目的: 胎児の状況を正確に把握し、将来の予測をたて、妊婦及びそのパートナーの家族形成の在り方等に係わる意思決定の支援を目的としています。
ノーマライゼーションの重要性: 出生前検査は一律に実施したり推奨したりするべき検査ではありません。ノーマライゼーションの理念を踏まえた適切なアプローチが求められます。

妊婦さんたちへの正確な情報提供: 妊婦さん、パートナーが検査について正しく理解し、熟慮のうえで判断できるよう、出生前検査に関する情報提供が必要です。
遺伝カウンセリングの重要性: 出生前検査を受ける際には、十分な説明・遺伝カウンセリングが不可欠です。
包括的な産科管理: どの出生前検査も、妊娠から出産までの全過程において、包括的な産科的管理と妊婦さんへの支援が必要です。
多職種連携によるサポート: 出生前検査を受ける妊婦さんたちへの支援は、産婦人科医だけでなく、各領域の専門医や専門職との多職種連携が不可欠です。
検査の正確さの確保: 出生前検査の正確性を担保するために、検査担当者による適正な検査手順と検査分析機関の精度管理が必要です。
胎児に先天性疾患が見つかった場合のサポート体制: 出生前検査によって胎児に先天性疾患が見つかった場合、もしくはその可能性が高いとされた場合は、医療、福祉、ピアサポートなどから妊婦さんやパートナーに寄り添う支援体制が地域ごとに整備されることが必要です。
一体的な体制整備: 出生前検査の実施体制は、検査実施のみならず、妊婦への事前の情報提供、遺伝カウンセリング・相談支援、検査分析機関の質の確保、検査後のサポートなど、一体的な体制整備が必要であり、一部の検査手法には認証制度の設置が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会報告書
令和3(2021)年5月 厚生科学審議会科学技術部会
NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
https://www.mhlw.go.jp/content/000783387.pdf
NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針
令和4(2022)年2月 日本医学会出生前検査認証制度等運営委員会
https://jams-prenatal.jp/file/2_2.pdf
出生前検査認証制度等運営委員会のロゴマークについて

認証医療機関および認証検査分析機関 は、 出生前検査認証制度等運営委員会のロゴマークを使うことができます。
円の中に描かれた波型の線は、「絆」や「つながり」を意味し、サポーターと親、そして小さな命とのつながりや支えをイメージしています。